胃がんは日本人に多いがんの一つで、今でこそ部位別死亡数の4位に位置していますが、かつてはがんによる死亡原因の断トツ1位でした。※1
胃がんは、発症部位や特徴によって、進行速度や治療方法が異なるため、見極めが非常に重要です。
本記事では、胃がんの概要をはじめ、主な種類や進行具合(ステージ)の判定方法、検査方法・治療法などを詳しく解説します。
胃がんに関する知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
胃がんとは?
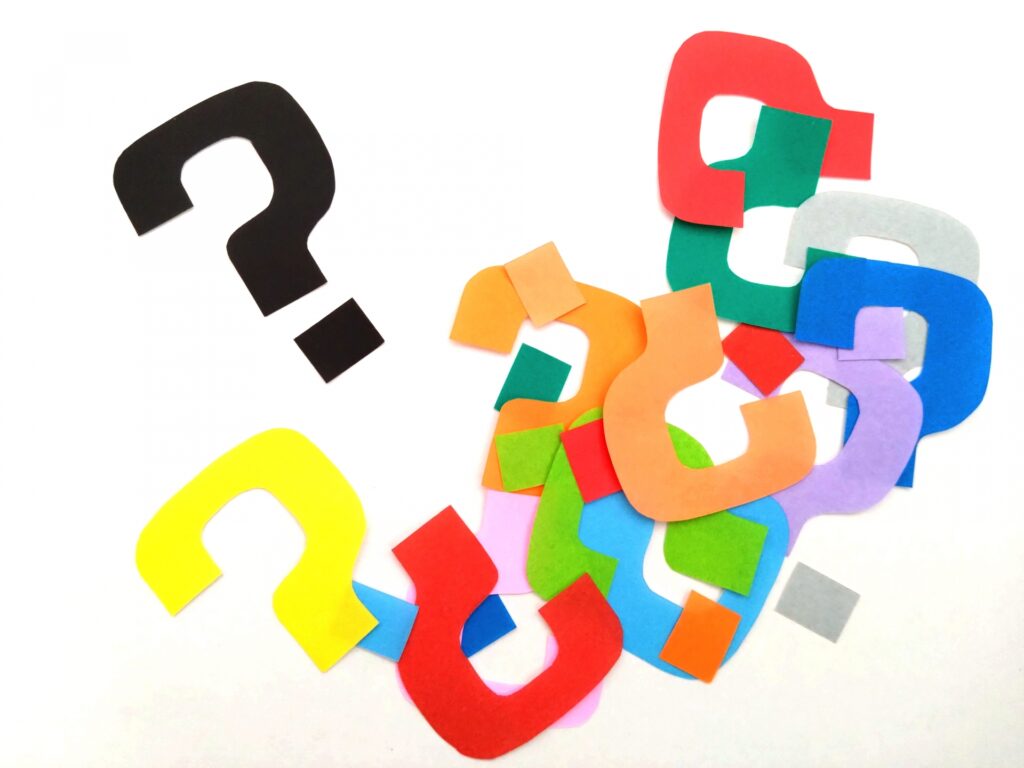
胃がんとは、胃壁の内側にある粘膜の細胞ががん化し、無秩序に増殖する疾患です。
部位別がん罹患数の3位に位置しており、全体の約95%は胃液を分泌する腺細胞に発症します。※2※3
早期の胃がんは、90%以上根治が可能です。※4
しかし、進行すると粘膜下層・筋層・漿膜下層・漿膜の深い部分までがんが広がり、大腸や膵臓などに転移するケースも少なくありません。
はじめに、胃がんの症状・原因・5年生存率を紹介します。
胃がんの症状
胃がんの代表的な症状は、下記のとおりです。
- 胃痛・胸やけ
- 胃の不快感・違和感
- 吐き気・嘔吐
- 下痢・便秘・血便
胃がんは、初期の自覚症状が出にくいです。進行すると胃やみぞおち周辺に痛みや不快感・違和感が現れて、吐き気や嘔吐、食欲不振が生じます。
また、がんから出血した場合は、貧血や吐血、黒いタール状の便(黒色便)を伴うケースが多いです。
そのほか、消化や吸収ができなくなることで体重が減少したり、水分の調整機能が低下して腹水が溜まったりなどの症状が現れます。
胃がんの症状は、胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎などと似ているため、見極めが重要です。気になる症状がある際は、内科や消化器内科で精密検査を受けましょう。
胃がんの原因
胃がんの原因には、次のようなものがあります。
- ヘリコバクター・ピロリ菌
- 喫煙・飲酒
- 食生活
日本人の胃がんの98%は、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染によるものです。※5
ヘリコバクター・ピロリ菌は、主に胃の機能が発達していない乳幼児期に家庭内で感染します。自然に消滅するケースは稀で、生涯にわたり感染は持続します。
感染者の胃がんリスクは5.1倍と非常に高いため、早期に除菌治療を受けることが大切です。※6
また、塩辛、漬物、魚卵、干物、味噌汁などは、3倍ほど胃がんのリスクを上昇させます。塩分濃度が高い食品を避けて、積極的に野菜・果物を摂取しましょう。※8
胃がんの5年生存率
胃がんの5年生存率は66.6%(男性:67.5%、女性:64.6%)と、全がんの64.1%とほぼ変わりません。※9
ステージ別の5年生存率は、下記のとおりです。
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | |
|---|---|---|---|---|
| 5年生存率 | 82.0% | 60.2% | 37.4% | 5.8% |
ステージ1の場合、治療効果を発揮しやすいことから5年生存率は82.0%と高い水準を維持しています。
一方、胃がんが胃の外に広がり、遠隔転移がみられるステージ4まで進行すると、5年生存率は著しく低下して5.8%になります。非常に厳しい状況といえるでしょう。
胃がんの主な種類

胃がんは、主に下記の3種類に分類されます。
- 分化型胃がん
- 未分化型胃がん
- スキルス胃がん
次章では、それぞれの特徴・原因などを詳しく紹介します。
分化型胃がん
分化型胃がんとは、胃の粘膜構造に近い形態でまとまって増殖するタイプです。高齢者の男性に好発し、大半は萎縮性の粘膜に発症します。
進行スピードが穏やかである分化型胃がんは、悪性度が比較的低いとされていますが、血液の流れにのって肝臓に転移するケースが多く、早期治療が重要です。
がんが胃の粘膜に留まっている場合は、体の負担が少なく、術後の早期回復ができる内視鏡的治療が可能です。
内視鏡的治療が困難な際は、がんの進行や健康状態に応じて、開腹による手術や化学療法、放射線治療、標的療法などを選択します。
未分化型胃がん
未分化型胃がんは、がん細胞が原始的な形状を保ちながら広がるように増殖します。若年層や女性に多く発症するタイプで、進行が速いことが特徴です。
また、がんが小さいうちからリンパ節や遠隔臓器に転移しやすい性質を持っているため、悪性度は高いといえます。
未分化型胃がんは、がんの範囲がわかりにくく、内視鏡的治療に適していません。一般的に、胃切除術に加えて化学療法や放射線治療が必要な場合が多いです。
スキルス胃がん
スキルス胃がんとは、胃の壁・組織全体が厚く硬くなる難治性のがんの一つで、女性や若年層でも発症するケースがあります。※1
一般的な胃がんと異なり、胃壁の内部を這うように広がる性質があることから早期発見が難しく、ある程度進行した状態で見つかるケースが少なくありません。
手術適応外の場合、化学療法や放射線治療、免疫療法などで症状の緩和を目指します。
スキルス胃がんは、ヘリコバクター・ピロリ菌の持続感染、喫煙・飲酒、食生活のリスク因子以外に、遺伝的な要因も大きく影響するため、家族歴を有する方は注意が必要です。
胃がんの進行具合(ステージ)の見極め方

胃がんの進行具合(ステージ)は、治療方針を決めるために非常に重要です。
下記の項目をもとに大きく1~4期に分類されます。
- 深達度
- リンパ節への転移
- 他の臓器への転移
次章では、それぞれの項目を詳しく解説します。
深達度
深達度とは、がん細胞が胃壁のどの深さまで達しているのかを示す指標です。
胃は、内側から粘膜層、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜の層で構造されており、深達度に応じて次の5つに分類されます。
| 深達度(T) | 状態 |
|---|---|
| T1(T1a・T1b) | がんが粘膜、もしくは粘膜下層に留まっている |
| T2 | がんが固有筋層まで浸潤して留まっている |
| T3 | がんが固有筋層を越えて漿膜下層まで入り込んでいる |
| T4a | がんが漿膜を越えて胃の表面に達している |
| T4b | がんが胃の表面に出て、ほかの臓器にも広がっている |
粘膜や粘膜下層に留まっているT1(T1a・T1b)は早期がん、そのほかはすべて進行がんです。がんが深く浸潤すると治療法の選択肢が狭まり、また、再発率も高くなります。
胃がんの深達度は、内視鏡検査・超音波内視鏡、CT検査などで確認が可能です。必要に応じて、病変部位より組織を採取して病理診断を実施して確定診断につなげます。
リンパ節への転移
胃がんは、胃の周辺のリンパ節に広がり、徐々に腹部大動脈や遠隔のリンパ節にまで転移します。
そのため、リンパ節への転移の有無・個数、がんの深達度を組み合わせて胃がんの進行度を判断します。
深達度 | 領域リンパ節への転移・個数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| なし(NO) | 1~2個(N1) | 3~6個(N2) | 7~15個(N3a) | 16個以上(N3b) | |
| T1(T1a・T1b) | 1A | 1B | 2A | 2B | 3B |
| T2 | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B |
| T3 | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C |
| T4a | 2B | 3A | 3B | 3B | 3C |
| T4b | 3A | 3B | 3B | 3C | 3C |
リンパ節への転移状況は、胸部・腹部CT検査、MRI検査、PET-CT検査などで調べることが可能です。
他の臓器への転移
胃がんが肝臓・肺・腹膜や遠隔の臓器に転移している場合、深達度やリンパ節への広がりにかかわらず、ステージ4と判定されます。
転移の状況により手術の対象になりますが、手術が困難なケースもあるため、薬物療法や放射線治療などで、症状の緩和やQOLの維持を目的とした治療がおこなわれます。
胃がんの一次検査の種類
胃がんの一次検査には、主に2つの種類があります。
- 内視鏡検査
- X線検査(バリウム検査)
ともに、胃がんにおける死亡減少効果が科学的に証明されています。
次章では、それぞれの検査の内容・費用などを詳しく紹介します。定期的に検査を受けて、初期の自覚症状が乏しい胃がんの早期発見を目指しましょう。
内視鏡検査
内視鏡検査は、超小型カメラを搭載した内視鏡を用いて体内の様子をモニターに映し出し、医師がリアルタイムで観察する検査です。
胃がんの一次検査の場合、口や鼻から内視鏡を挿入する胃内視鏡検査(胃カメラ)がおこなわれます。
胃内部の粘膜の状態をはじめ、色・形、隆起や凹みの有無などを詳しく観察でき、がんはもちろん、炎症や潰瘍などの発見にもつながります。
万が一、疑わしい病変が見つかった場合は、検査時に組織の一部を採取して生検をおこなうことが可能です。
所要時間は30分程度ですが、より正確に検査するために検査前夜~当日まで絶食します。
また、鎮静剤を使用した際は、検査後に1時間程度の安静が必要であり、自動車・自転車などは終日運転できません。
内視鏡検査は、症状があれば保険診療で受けられますが、健康診断や人間ドックなど、任意で検査を受ける際は自由診療になります。
X線検査(バリウム検査)
X線検査(バリウム検査)は、造影剤(バリウム)と発泡剤を飲み、X線を照射して多方面から撮影する検査です。
胃の位置・形や粘膜の様子・凹凸などの確認ができ、がんをはじめとする病変の発見につながります。
所要時間は15分前後で、検査前は胃液の分泌を抑えるために絶食し、検査後は造影剤を排出する下剤の服用が必要です。
X線検査(バリウム検査)は、胃の異常が疑われる場合は公的保険が適用されますが、とくに症状がなく、任意で受診する際は完全自己負担の自由診療になります。
「要精密検査」の判定を受けたら、胃内視鏡検査(胃カメラ)による再検査を受けることが大切です。
胃がんの治療法の種類
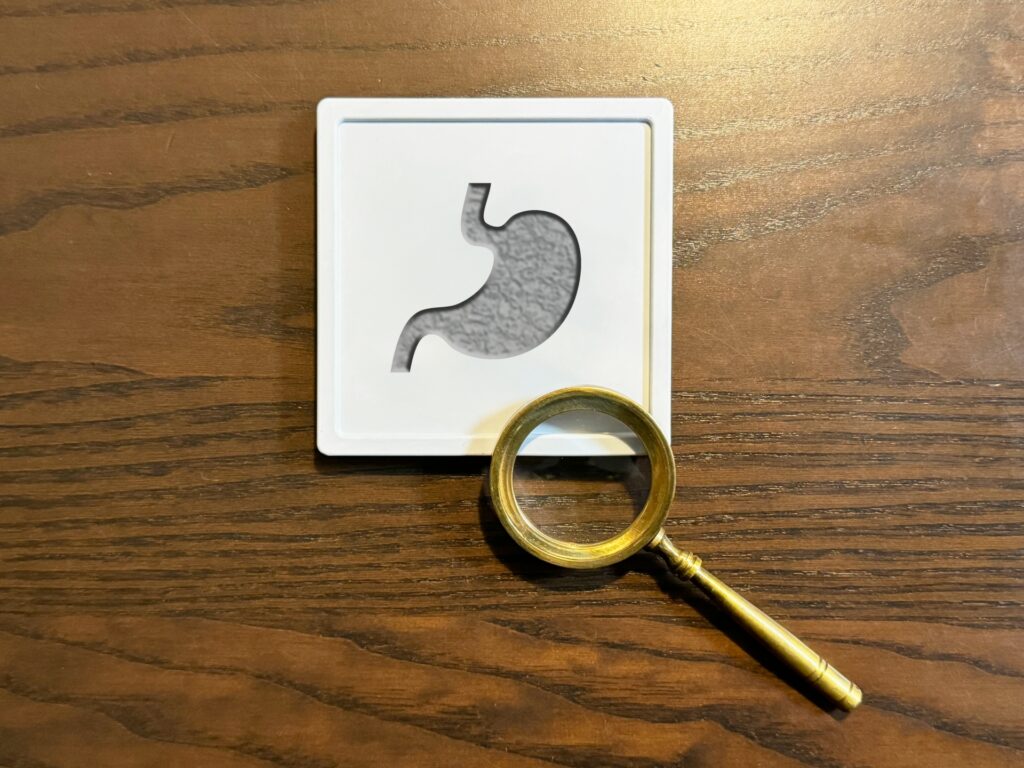
胃がんはがんの進行具合(ステージ)に応じた治療を基本とし、患者の年齢・希望・体の状態を考慮したうえで総合的に検討します。
主な治療法は、内視鏡的粘膜切除、手術(外科治療)、化学療法です。
また、複数の治療法を組み合わせる集学的治療をおこなう場合もあります。集学的治療は、単独より治療効果が高いケースがあり、臓器の温存、再発の防止にもつながる治療法です。
次章では、それぞれの治療法を詳しく解説します。
内視鏡的粘膜切除
内視鏡的粘膜切除術(EMR)とは、内視鏡を用いて粘膜下層のレベルでがんやポリープを一括切除する手法で、内視鏡治療の一つです。
局所注射でがんの下(粘膜下層)に生理食塩水を注入して隆起させ、内視鏡のスネアワイヤーを病変の根元にかけて締め上げ、高周波電流で切除・回収します。
切開や全身麻酔の必要がないため、開腹手術に比べて体の負担が軽く、また、1週間程度で社会復帰が可能です。
胃がんにおいては、下記が内視鏡的粘膜切除術の対象です。
- がんが粘膜に留まっており、リンパ節に転移がない
- 隆起は2cmまで、陥凹は1cmまでのがん
- 潰瘍のない早期胃がん
がんの大きさにより、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を検討します。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)は、粘膜内に留まるがんであれば大きさを問わず切除でき、潰瘍が伴う場合でも3cm以下のがんであれば適応内です。
根元に茎やくびれがある10mm未満のがんには、日帰り手術のポリペクトミーが適応となります。
手術(外科治療)
手術(外科治療)は、がんを含めた胃の一部、またはすべてを切除してがんを確実に取り除く治療法です。
がんの発症部位やリンパ節への転移などに応じて、下記の切除方法を検討します。
- 胃全摘術
- 幽門側胃切除術
- 幽門保存胃切除術
- 噴門側胃切除
胃上部または幽門側にかかる進行がんに対しては、胃および周囲のリンパ節をすべて切除する胃全摘術をおこないます。
全摘後は、食道に胆汁や膵液が逆流しないよう食道と小腸を吻合する再建術「ルーワイ法」をおこないます。
幽門側胃切除術とは、幽門を含む胃の出口側の約2/3を切除する方法です。必要に応じて周囲のリンパ節も取り除き、残った胃と十二指腸、または小腸をつなぎ合わせます。
幽門保存胃切除術は、幽門・噴門から5cm以上離れた胃中部のがんが対象です。胃の機能が保たれることで、術後のダンピング症候群や体重減少が予防できます。
胃上部や食道胃接合部のがんには、胃の2/3以上を温存できる噴門側胃切除を選択します。
手術後は、食道と残った胃を吻合して逆流防止弁のような構造をつくり、小腸とつなぎ合わせる「ダブルトラクト法」が必要です。
化学療法
胃がんが他の臓器に転移したり、再発したり、手術で根治が難しい場合は化学療法をおこないます。
がんの進行抑制・症状の緩和を目指して、次の薬剤が用いられます。
- 細胞障害性抗がん薬
- 分子標的薬
- 免疫チェックポイント阻害薬
そのほか、がんの縮小を目的とした術前補助化学療法があります。
手術前に細胞障害性抗がん薬を用いてがんを小さくすれば、遺残なく取り除ける可能性が高いです。
また、手術後に術後補助化学療法をおこなえば、目に見えない微小ながんを完全に破壊でき、がんの再発が防げます。
胃がんの早期発見にマイクロCTC検査がおすすめ

マイクロCTC検査は、胃がんをはじめ、全身のがんリスクがわかる画期的な血液検査です。
血中に漏れ出したがん細胞そのものを捕捉して個数を明示するため、従来のがん検査では見つけにくい小さながんや、無症状な早期がんの発見につながります。
ここからは、マイクロCTC検査の特徴を紹介します。
早期発見が大切な理由
がんは進行具合(ステージ)が進むほど進行速度が速くなります。
がんは、発生後10~15年ほどかけて1cmの大きさに成長しますが、1cmから2cmに成長するまでの期間は1年半程度です。
一般的に、2cm以上に成長した進行がんは、さらに分裂・増殖の速度をあげ、全身のさまざまな臓器に転移するため治療が困難になります。
とくに、胃がんのように特有の症状がない場合、早期の発見が遅れて気付かないうちに進行しているケースが多く、命を守るうえでも早期発見は非常に大切です。
しかし、従来の検査では、1cm未満の小さながんは発見できません。また、画像に写りにくい部位のがんを見落とすケースもあります。
マイクロCTC検査の場合、世界有数のアメリカのがん研究治療施設「MDアンダーソンがんセンター」が開発したCSV抗体を用い、独自の検査手法を導入しています。
そのため、血中を循環する微小ながん細胞を1個単位で捉えることが可能です。
定期的にマイクロCTC検査を活用して、がんの早期発見・早期治療を目指しましょう。
検査は1回5分の採血のみ
マイクロCTC検査は、1回5分の採血のみで全身のがんリスクがわかるため、次の方におすすめです。
- 仕事や家事が忙しい方
- 育児中で自身の時間が取りにくい方
- 検査を受けることが面倒な方
健康診断や人間ドックで全身のがんを調べる場合、半日~1日程度の時間を確保する必要があり、仕事・家事・育児などで多忙なときは受診を後回しにしがちです。
また、食事制限をしたり、検尿・検便などの事前準備をしたり、検査が面倒と感じる方もいるでしょう。
マイクロCTC検査は、血中を循環するがん細胞そのものを捉えることから、食事制限や事前準備は不要です。
そのほか、24時間365日予約ができ、問診票の記入・支払い・検査結果の確認までWebで完結します。
手間をかけずに手軽に検査が受けられる点も、マイクロCTC検査の魅力の一つです。
全国のクリニックで検査可能
マイクロCTC検査は、全国の提携クリニックで導入しており、専門の医療機関や遠方の検査施設を受診する必要はありません。
住居地・勤務地の近所クリニックはもちろん、外出先や出張先などの都合のよい場所で同様の検査が受けられます。
マイクロCTC検査の流れは、次のとおりです。
- クリニック検索・予約
- 検査(採血)
- 検査結果の確認
マイクロCTC検査は完全予約制です。まず、マイクロCTC検査の公式サイトから受診するクリニックと日時を選び、問診票を記入後、支払い方法を選択して予約を確定させます。
検査当日は10分ほど前に来院して受付を済ませましょう。
検査結果の確定は、2週間前後です。登録先のメールアドレスに通知が届いたらマイページにログインし、内容を確認しましょう。
がん細胞が検出された場合、医師による無料相談が受けられるため万が一のときも安全です。
胃がんに関するよくある質問
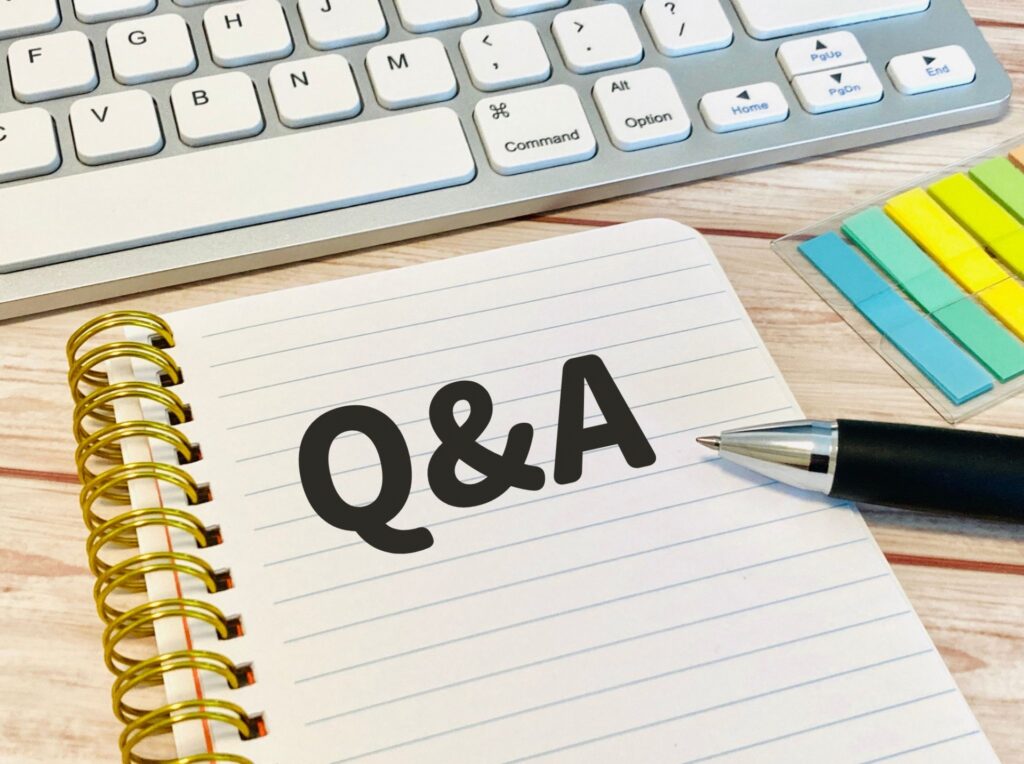
最後に、胃がんに関するよくある質問を紹介します。
同じ疑問を抱いている方はもちろん、胃がん検診に関する情報を知りたい方はぜひ参考にしてください。
胃がん検診は何歳から受けるべき?
胃がんは、男女ともに70歳以上の高齢者に多い病気です。※11
しかし、40~50歳代から胃がんの罹患数は増加し始めるため、国は定期的な胃がん検診を推奨しています。
企業の健康診断や人間ドックなどで胃がん検診を受診する機会がない場合は、自治体の検診を利用しましょう。胃がん検診の内容や対象者は、自治体により異なります。
| 内容 | 対象者 | 受診間隔 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| X線検査(バリウム検査) | 40歳以上 | 2年に1回 | 1,200円 |
| 内視鏡検査 | 50歳以上 | 2年に1回 | 2,000円 |
| リスク検診 | 50~75歳 | 5年に1回(一生に1回) | 700円 |
検診対象者には受診券が郵送されます。有効期限内に胃がん検診実施医療機関を予約して、胃がんの早期発見につなげましょう。
胃がん検診は毎年すべき?
一般的に、胃がん検診は毎年受ける必要はなく、2年に1回の受診が推奨されています。
しかし、次に該当する方は胃がんの高リスク群に分類されるため、受診間隔を調整する必要があります。
- ヘリコバクター・ピロリ菌の保有者
- ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療を受けた方
- 過去に早期胃がんの治療を受けたことがある方
- 血液検査(ABC検診)で胃がんのリスクが高いと評価された方
自身の受診間隔を知りたい方は、医師・看護師に相談しましょう。
胃がんの前兆・前触れはある?
胃がんは、初期の自覚症状に乏しく、また、前兆・前触れとなる特有のサインはありません。そのため、定期的に検査を受けることが大切です。
胃痛・胸やけなどの気になる症状が続く場合は、早めに医師に相談し、適切な検査を受けましょう。
まとめ

本記事では、胃がんの種類や進行具合の見極め方を中心に解説しました。
胃がんには、主に分化型胃がん・未分化型胃がん・スキルス胃がんがあり、増殖パターンや細胞の特徴などで分類されます。
とくに、進行が速い未分化型胃がんと早期発見が困難なスキルス胃がんには注意が必要です。
初期の症状が出にくい胃がんの早期発見には、マイクロCTC検査がおすすめです。
マイクロCTC検査は、血中のがん細胞そのものを捉え、個数を1個単位で明示する検査です。1回5分の採血のみで、胃がんを含むすべてのがんのリスクがわかります。
定期的にマイクロCTC検査を活用し、従来の検査では見つけることが難しい1cm以下のがんの発見につなげましょう。
〈参考サイト〉
※1、※2:国立がん研究センター がん統計|最新がん統計
※3:MSDマニュアル家庭版|消化器系の病気 胃がん
※4:新潟県立がんセンター新潟病院|がん・疾患情報サービス
※5:日本癌学会|第23回日本癌学会市民公開講座「胃がんで亡くならないために何をなすべきか」
※6:国立がん研究センター|がん対策研究所 ヘリコバクター・ピロリ菌感染と胃がん罹患との関係
※7:国立がん研究センター|がん対策研究所 たばこ・お酒と胃がんの関連について
※8:国立がん研究センター|がん対策研究所 食生活パターンと胃がんとの関連について
※9:国立がん研究センター|集計表 地域がん登録によるがん生存率データ(1993年~2011年診断例)
※10:がん情報サイト「オンコロ」|スキルス胃がんの基礎知識
※11:国立がん研究センター|がん統計 胃












